> [!NOTE] 過去ブログ記事のアーカイブです
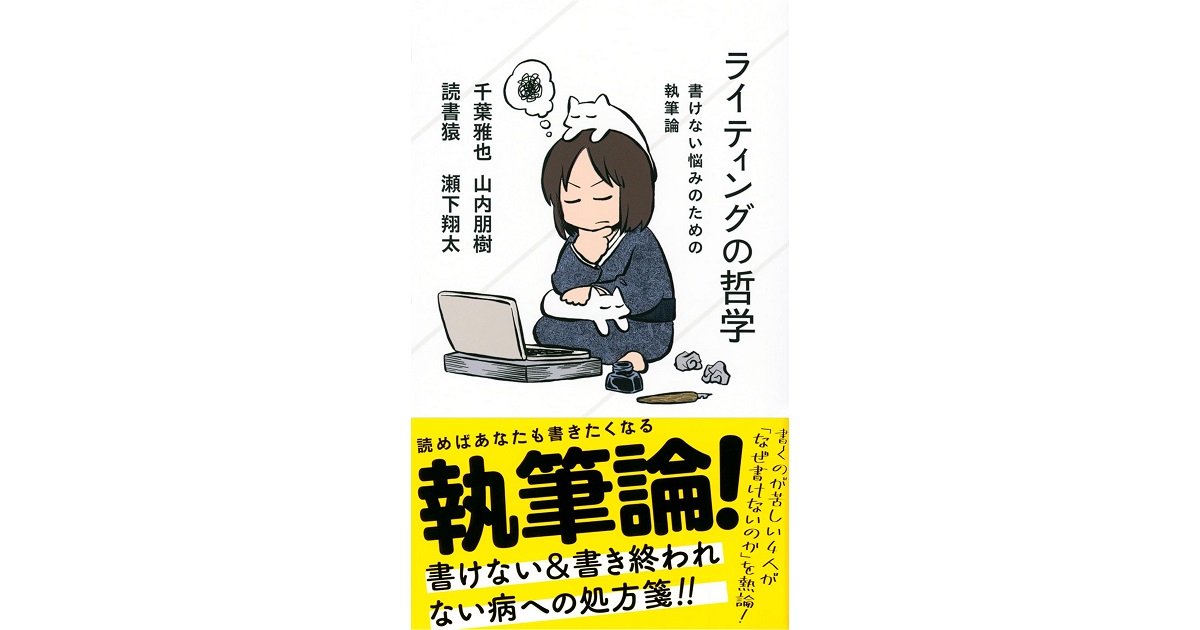
**『ライティングの哲学**』読みました。すごく良かったです。
[ライティングの哲学 書けない悩みのための執筆論 (星海社新書) | 千葉 雅也, 山内 朋樹, 読書猿, 瀬下 翔太 |本 | 通販 | Amazon](https://amzn.to/3hqCnzi)
「読めばあなたも書きたくなる」と帯にありますが、ほんとに書きたくなれました。
この本の秀逸なところは書けなくて悩んでる人々に「適当に自由に書いていいんだよ」という許しを与えてくれることですね。
本書内でも触れられているように、世にある文章術の本は「これをしちゃダメ」「こうしなさい」という禁止や制約をする方向性のものが多い。
でも、この本は、既にプロの書き手であるはずの参加者たちでさえ四者四様に書くことに対し苦悩し、そしてそれぞれのやり方で一般的な束縛から抜け出て、その人なりの書き方に歩んでいく姿が描かれています。
これによって、読者も書き方に正解なんてないし自分なりのやり方でやればいいんだと安心感が得られるんですね。
ああしなきゃ、こうしなきゃと身構えれば身構えるほど、文章って出てこない。
とにかく形は気にせず出すのが大事なんだと。
もちろん、制約にも意味はあって、「締切」がその代表ですね。
本書内でもとくに読書猿氏が触れられてたと思うのですが、「締切」によって制約を作ることで「断念」が得られることの効果は大きい。
江草も以前毎日ブログ更新というのをやってましたが、実は「時々更新しよう」とするよりよほど楽だったんですよね。
毎日更新というのは要は毎日締め切りが来るわけです。
「完成度はともかくとにかく何でもいいから書こう」そういう「断念」が常にあります。
「時々更新でいい」とすると、かえって「もっといい文章にまとめられたらアップしよう」となって、永遠に完成度を求めて潜水することになりがち。
自分の文章のクオリティが気になって、延々と書き直していたり、なんなら逆に怖じ気ついて書けなくなったりします。
自由といってもほんとうに完全に自由にするのは「無限の可能性」に圧倒されてそれはそれで書けなくなるので、制約も確かに必要なのです。
つまり、
「テーマ自由」「締め切りないのでいつでも気が向いたときに書いてください」「どんな文体でもOK」という自由すぎる環境でも、
「テーマはこれで、この要素とこの要素とこの要素を文章に含めてください」「締め切り厳守」「文体はこれに統一、こういう形式は避けてください。禁止事項は……」「絶対に読者にウケるように」「ポリコレに配慮し炎上は避けてください」などのように制約だらけの環境でも、
どっちでも人は書けません。
だから結局重要なのはバランスなんですよね。
自由と制約のバランス。
このバランスが、それぞれの個人に合った特性で仕上げられているか、これがキモなんだと思うんです。
本書の4人もそれぞれ全く異なる個性的なアプローチで書くことに向き合ってますしね。
その人に一番フィットするようにうまく制約を配置すること、文章を逆に引き出す足場になるための制約を築くこと、それが大事なんですね。
もちろん、この自分らしいバランスを見出すのは簡単ではありません。
でも、それに向かう道筋はいわば「クエスト」であって、それ自体をゲーム的に楽しむ気持ちでいれば楽しいと思うんですよね。
自分自身で誰に言われるまでもなく自分に最適な書き方を見出す大冒険。
江草も自分なりの書き方の記事を過去にアップしたことがありますが、こういうのを考えてうまくいったときは本当に楽しいです。
[[150日以上毎日記事を書き続け行き着いた、ブログの効率的な書き方「転記法」]]
というわけで、本書『ライティングの哲学』にあてられて、自由にゆるく書きなぐった本記事ですが、どうでしょうね。
たしかに、いつも以上にぐにゃぐにゃっとした記事にはなってしまったかもしれませんが、ほんと気楽に書けば文章ってのはすぐ書けるもんなんですよね。
LINEの雑談や買い物メモが書けない人はほとんどいないのですから、ブログ記事も多分これぐらい気楽で良いものなのでしょう。
本書で得た気づきを踏まえ、また今後も自分なりの書き方を模索していこうと思います。
以上です。ご清読ありがとうございました。
#バックアップ/江草令ブログ/2021年/9月