> [!NOTE] 過去ブログ記事のアーカイブです
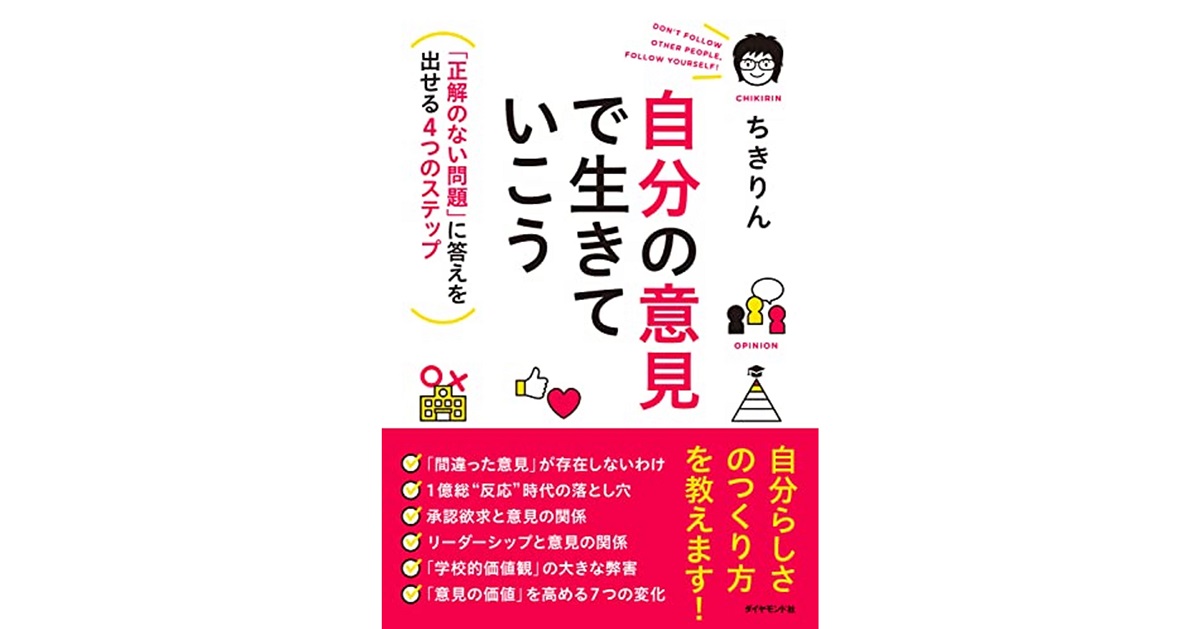
社会派ブロガーちきりん氏による新刊『自分の意見で生きていこう――「正解のない問題」に答えを出せる4つのステップ』読みました。
[自分の意見で生きていこう――「正解のない問題」に答えを出せる4つのステップ | ちきりん |本 | 通販 | Amazon](https://amzn.to/3IdBHbr)
ちきりん氏による「大事なスキルシリーズ」第4弾にして最終作です。
今回のテーマは「意見」。
自分の意見を持つこと、表明することの大切さを語られています。
「意見を持つ」とは「ポジションをとる(リスクをとる)こと」だと述べる、ちきりん氏独自の定義が特徴的です。
SNS時代にあって、意見を表明するのではなく反応をするだけの人が多いことに警鐘を鳴らし、インフルエンサーになることや承認欲求を満たすことが目的ではなく、自分が自分であるためにこそ意見を持つのだと、最終的に熱い人生論にまで至る一冊です。
とても面白かったです。
さすがのなめらかな筆致で、意見を持つことの大切さを分かりやすく、そして説得的に書かれてるなと感じました。
自我の確立と承認欲求の話なんて、大変に難しい哲学的テーマなのに、ちきりん氏らしくすごくきれいに整理されてます。奥深いテーマを一般向けでここまでわかりやすく書けるのはまさに脱帽です。
こんなにわかりやすく読者に提示するのは、下手に専門用語を使って煙に巻くよりはるかに難しいはずで、このあたりがちきりん氏の真骨頂ですね。
しかも、どこにも嫌味を感じさせず、「よし自分の人生を生きよう」と自然とポジティブな気持ちにさせる読後感は天才的ですね。
この辺、他書にしばしば見受けられる、他人への人格批判やマウンティングを排してるちきりん氏のスタイルのとても良い点だと思います。
「意見を持つこと」を「ポジションをとること」とする定義も極めて面白いですね。
この定義を明確化されることによって、読者は「発言する時に自分はポジションを取ってるだろうか」と否応なしに考えさせられることになります。
たとえば、本書のちきりん氏の個々の意見にも「ほんとうにそうか?」とツッコミを入れることはできるでしょう。
ただ、その場合に自分は「反応」でなく「意見」で返せてるか、ちきりん氏のようにポジションを取った上でツッコミを入れることができているか、自然と試されてしまうのです。
ひとたび読んでしまったら「意見を持つこと」すなわち「ポジションを取ること」を意識せざるをえない、魔法のような一冊と言えるでしょう。
本書で特に秀逸だなと思ったのが「どんな意見にだって反応であれば何も考えることなく返せる(なんならその意見を見ることさえなく)」という指摘です。
> ちなみにみなさん、なにか私に「意見」を言ってみてください。なにについてでもかまいません。自分のアタマでしっかり考えた意見を表明してみてください。私はそのあなたの意見に、なにも考えることなく、こう言うことができます。「そう? そうとも言えないと思うけど」
>
> ちきりん.自分の意見で生きていこう――「正解のない問題」に答えを出せる4つのステップ(p.80).ダイヤモンド社.Kindle版.
確かに何にでも返せる無敵の反論というのは存在するんですよね。
だからこそ、意見を持つ、ポジションを持たないと意味がないというのは、まことに正論と思います。
江草もよく「反応」でコメントしてしまうことは多いので、耳が痛いお話です。
また、パートナーから「どう思う?」と尋ねられ「うーん、君に任せるよ」と答えた時、なぜ怒られてしまうのか、と、家庭運営での意見の大切さを説く箇所も面白かったです。
> 「自分の意見を表明し、議論する」プロセスに貢献できない人は、仲間ではなく、作業担当者に過ぎないのです。
> 家庭においても同じです。「風呂掃除とゴミ出しを担当している」のは、家事分担ではあっても家庭運営への参画(貢献)ではありません。家庭運営の構成員(=仲間)とは、「家事をどのように分担すべきか」についての意見を表明でき、それについてパートナーと議論できる人なのです。
>
> ちきりん.自分の意見で生きていこう――「正解のない問題」に答えを出せる4つのステップ(p.188).ダイヤモンド社.Kindle版.
家事の作業をしているだけでは不足で、家庭運営についての意見を表明することこそが参画しているとみなされる条件だという、ちきりん氏の鋭い指摘です。
まったく仰る通りと思います。
同様に、民主主義社会において自分の意見を持たない者(持とうとしない者)は、事実上、社会運営に参画してないわけだから民主主義社会へのフリーライダーと言われても仕方ないとも言えるのではないかと江草は考えています。「仕事をして税金を納めてさえいれば十分に社会に貢献してる」と考えてる人が少なくなさそうなのは危ういなと。
家庭運営に限らずそういう広い示唆を与えてくれる点でも、非常に良い指摘ですね。
そういえば、ちきりん氏の著作は基本的に引用とか無いのですよね。
最近の流行りのビジネス本にありがちな、「○○大の研究によれば」とか「○○が語ってるように」とかもほとんどない気がします。
おそらく、別にちきりん氏がまるで何も読んでない、何もインプットしてないわけではなくて、これは、他人の言葉をそのまま使わず自分の言葉に変えること――すなわち自分のアタマで考えて、自分の意見として言葉を紡ぐこと――にこだわってるちきりん氏のポリシーの現れなのかもしれませんね。
そういう意味では、江草は普通に引用も「誰それがこう言っていた」も多用するので、まだまだ考えたりてないということなのでしょう。反省反省。
もともと江草がちきりん氏のファンなのもあって、正直甘めの感想になったかもしれませんが、やっぱりどうしても面白かったので仕方ありません。
読みやすい文体、分量ですし、「意見を持つこと」の意義を感じるために『自分の意見で生きていこう』は多くの人にオススメです。
[自分の意見で生きていこう――「正解のない問題」に答えを出せる4つのステップ | ちきりん |本 | 通販 | Amazon](https://amzn.to/3rwzvVL)
以上です。ご清読ありがとうございました。
#バックアップ/江草令ブログ/2022年/1月